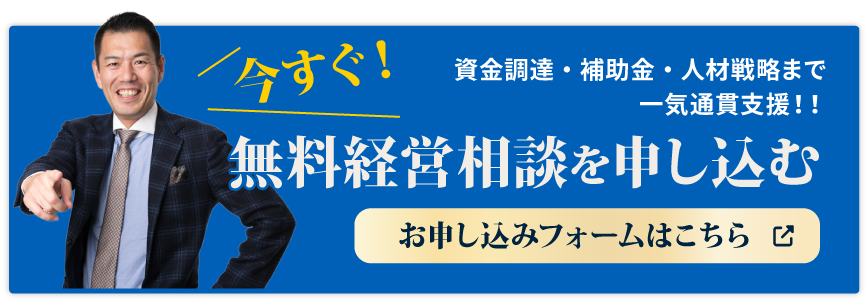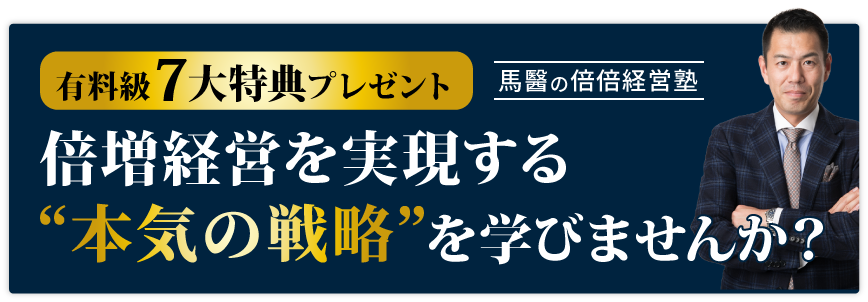「みなし退職金」に注意。形式だけの退任は税務で否認される?
経営者の退任や代替わりの際、長年の功労に報いる形で退職金を支給することはよくあります。
しかし、「形式上は退任しているのに、税務上では退職と認められない」ケースが存在します。
これが、いわゆる 「みなし退職金(退職否認)」 です。
支給額が大きいだけに、判断を誤ると法人税の追徴課税や経営上のトラブルにつながりかねません。
本記事では、その基本的な考え方と注意すべきポイントを整理します。
退職金が「退職」と認められるための前提
法人税基本通達では、役員の退職金は 「実質的に退職した」と認められる場合 に限り、
損金(経費)として扱うことができます。
ここでの「実質的」とは、経営から完全に離脱している状態を指します。
たとえば次のような条件が満たされている必要があります。
- 経営判断や意思決定に関与していない
- 社員や役員の人事に関与していない
- 銀行口座や印鑑の管理から外れている
- 会社の借入保証や契約責任から解放されている
単なる登記上の退任や肩書の変更では、退職とはみなされません。
「みなし退職」と判断される主なパターン
税務上、次のような実態がある場合は「退職金ではなく給与」とされるおそれがあります。
| 状況 | 税務上の見方 |
|---|---|
| 退任後も会社に頻繁に出社している | 実質的に経営関与 |
| 銀行取引・資金決済に関与 | 経営判断の継続 |
| 社員の採用・昇給を承認 | 人事権の行使=経営関与 |
| 会社の借入に引き続き保証人として署名 | 経営責任の継続 |
| 株式・議決権を多く保有 | 実質的支配権の維持 |
このような場合、税務署は「形式だけの退任」と判断し、
退職金を損金不算入(経費として認めない)とする可能性があります。
税務調査でチェックされるポイント
退職金の支給が適正かどうか、税務署は以下を重点的に確認します。
- 退職の経緯と支給の理由(議事録・支給理由書など)
- 勤続年数・役職・最終報酬に照らした支給額の妥当性
- 退職後の実態(出社頻度・発言力・決裁権)
- 株式・保証・人事権などの整理状況
形式的な退任ではなく、実態として経営から退いているかどうかが判断の軸になります。
リスクを防ぐための3つの整備ポイント
① 退職金規程の整備
勤続年数や役職ごとの支給倍率など、支給基準を明文化しておく。
社内ルールとして整っていれば、恣意的支給とみなされにくくなります。
② 経営関与・保証関係の整理
退職後は銀行保証や印鑑権限、決裁権を速やかに新経営者へ移譲。
「名実ともに退職」と言える体制を作ることが大切です。
③ 議事録・契約書の作成
役員会・株主総会での決議を記録し、支給理由書を添付。
税務署に対しても正当性を説明できる資料を残しておきましょう。
退職金支給のタイミングと調査リスク
税務調査では通常、過去3〜5年の取引が対象です。
ただし、経営関与が継続している場合は、過去の支給分も参照されることがあります。
退職金の支給は「今後の税務調査を見据えて準備する」ことが重要です。
まとめ:退職金は「経営からの完全離脱」が前提
退職金を安全に支給するためには、
登記や肩書の変更だけでなく、経営権・人事権・保証・株式の整理が欠かせません。
税務署は「形式」ではなく「実質」を見ています。
経営と所有を明確に分け、退職を“事実として成立させる”ことが、
経営者・後継者双方の安心につながります。
▼▼ご相談フォームはこちら(スマホで簡単入力)▼▼
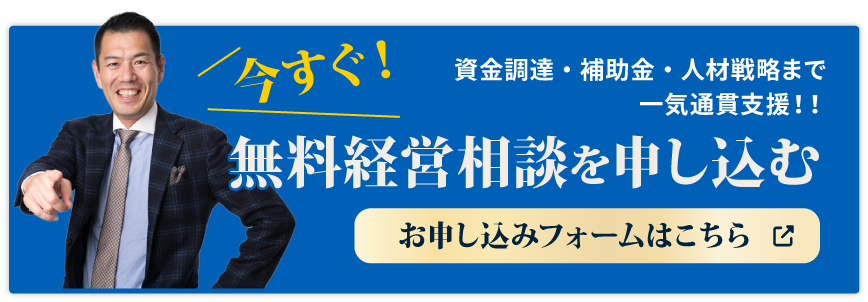
※ご相談内容に「みなし退職金」とご記入いただけるとスムーズです。